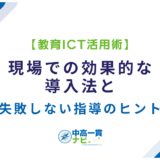はじめに
「公立一貫だけでは一発勝負で不安」「私立も“適性型”で受けられる?」——ここ数年、こうした声に応える形で首都圏の私立中で「適性検査型入試」や“思考力型”の導入がじわり拡大しています。東京都内でも、安田学園や文京学院大女子などが公立一貫の対策を活かせる入試枠を設け、2月入試の併願先として選びやすくなってきました。学校横断のまとめ記事や特集ページも増え、比較がしやすい環境に。この記事では、最新の公式情報をもとに「何がどう広がっているのか」「どこをどう選ぶか」を整理し、現場で役立つ“使い方”まで丁寧に解説します。
1. ニュース概要:私立で広がる“適性検査型”という選択肢
近年、公立中高一貫の適性検査に近い形式(資料読み取り・条件整理・記述等)で評価する私立の入試方式が拡大。東京都では安田学園が「適性I・II・III」型を複数学期で実施し、募集人数も明確に掲示。文京学院大女子は「公立一貫との併願をお考えの受験生に」と適性検査型枠を公式に案内しています。横断的な“実施校一覧”や特集記事も複数公開され、トレンドが可視化されつつあります。
2. どの学校が“適性型”を実施?(例とソース)
東京都内の私立で適性検査型や近縁の“思考力型・PISA型”を掲げる学校が複数確認できます。例として、安田学園は「適性検査型(I・II・III、各45分)」を公式要項に明記。文京学院大女子は「公立一貫との併願を想定した適性検査型」を公表し、募集要項PDFにも“適性検査型入試”の記載があります。加えて、学校横断で実施校を整理する記事やデータベースもあり、候補校の洗い出しに使えます。
3. なぜ拡大?——背景にある3つの動き
“適性型入試”を導入する私立中学校が増加している背景には、教育・入試の構造的な変化があります。特に、「公立一貫校の人気」と「1校勝負を避けたい保護者層」の受け皿として私立の役割が広がっている点が重要です。さらに、学校側の評価軸の多様化や受験情報の整備も後押しとなり、適性型入試は今後も定着・拡大していく見通しです。塾・家庭ともに情報のアップデートが求められています。

- 公立一貫人気と“一発勝負”回避ニーズ
公立一貫は受検機会が限られるため、2月の私立で“適性型”を受けて合格を確保したい層の需要が拡大。私立がその受け皿を設け始めた構図です。 - 学校側の評価軸多様化
従来の教科型だけでは測りづらい思考・表現・協働などを評価したい学校が、適性型や思考力型を導入。解説記事でも“私立にも広がる”とされます。 - 受験情報の整備
実施校一覧・模試情報・解説ページが出そろい、保護者の比較検討が容易に。
4. どう選ぶ?——“適性型”私立の見極め方
適性型入試を導入する私立中学校を選ぶ際は、公立との形式の近さだけでなく、返却体制や日程の柔軟性まで含めた見極めが必要です。たとえば、「適性I・II・III」など形式が明示された学校は対策しやすく、解き直しの効果も高まります。また、2/1〜2/4の試験枠や複数回実施の有無も併願計画に直結するため、実務的な選び方が結果を左右します。
(1) 形式の近さ:公立一貫の適性A/B/C/Dにどの程度近いか(資料読み取り、複合設問、記述比率)。安田学園のように「適性I・II・III」を明示するタイプは形式が把握しやすい。
(2) 返却と講評:答案返却・講評・模範解答の有無は“解き直し”の質を左右。
(3) 併願カレンダー:2/1〜2/4の時間帯(午前/午後)や複数回実施の有無を確認。文京学院大女子のように適性型の回を別枠で設ける学校は組みやすい。
5. 公立対策が“そのまま”使えるのか?(活用の勘所)
“適性型”を掲げても学校ごとに配点・設問設計は違うため、最後は公式要項で仕様を確定し、学校別の過去問・サンプルで最終調整を。とはいえ、共通して効くのは資料読解→条件整理→記述で筋道を示すという“適性の基本”。公立向け演習を私立の想定時間・枚数に合わせて縮約リハーサルするのが現実的です。横断特集も“私立に広がる適性型”の背景を整理しており、設問の思想を掴む助けになります。
6. 塾・予備校関係者への注目点
“適性型”私立の拡大に対応するには、公立対策との両立を見据えた教材開発と運営設計が不可欠です。
① 公立対策×私立併願の“両用教材パッケージ”
資料読解・表/グラフ・条件整理・論理記述をコアに、時間配分と用紙枚数を私立仕様にチューニングした演習セットを準備。答案返却テンプレートは採点観点(根拠・論理・表現)を統一し、ステップごとの到達度が見える設計に。
② 年間カレンダーを“私立の実施日”に同期
2/1〜2/4の適性型実施枠を基点に、直前2週=演習縮約/試験週=負荷軽減/翌週=解き直し集中のサイクルを固定。学校横断の特集・データベースで日程を早期確認し、個別面談で併願ルートを可視化。
③ 会場協力・合同解き直し会で集客導線を作る
地域の私立と連携し会場協力や解き直し会を共催すれば、来場→体験授業→個別面談の導線を設計しやすい。適性型模試や学校特集とのコラボを活かし、広域母集団と接点を持つ。
まとめ
私立で広がる“適性検査型入試”は、公立一貫の一発勝負リスクを和らげる併願の受け皿として実用度が高まっています。実施校は年ごとに入れ替わるため、横断特集で候補を洗い出し→各校の公式要項で最終確認が鉄則。指導現場は、公立対策をベースに私立の時間・分量へ縮約した演習、実施日同期の年間設計、解き直し会の仕組み化で“受けて終わり”を防ぐことが鍵です。併願の選択肢が増えた今こそ、情報を地図に変え、戦略的に歩む準備を整えましょう。
参考・出典
- 安田学園中学校「中学入試募集要項(適性検査型:適性I・II・IIIを実施)」、募集人数・時程等。 yasuda.ed.jp
- 文京学院大学女子中学校「中学入試|適性検査型入試(公立一貫との併願向け)」および募集要項PDF。 hs.bgu.ac.jphs.bgu.ac.jp
- インターエデュ特集「私立校にも広がる『適性検査型入試』/実施校一覧」。 インターエデュインターエデュ
- 首都圏模試センター「適性検査型模試(判定対象に“その他私立”を含む)」—私立の適性型動向に関する連載・学校特集。 syutoken-mosi.co.jpsyutoken-mosi.co.jp
注:実施の有無・方式・日程は毎年更新されます。最終情報は各校の最新公式要項をご確認ください。